| World > Africa > Democratic Republic of the Congo | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Franco et O.K. Jazz (1956-89) | ||||||||||||||||
|
Madilu Bialu System, vocal (1980- ) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Artist | ||||||||||||||||
|
LES CHAMPIONS DU ZAIRE |
||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
|
HOMMAGE A FRANCO O.K. JAZZ |
||||||||||||||||
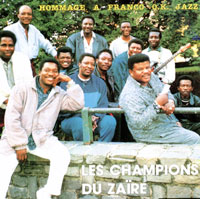 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Review |
||||||||||||||||
|
このサイトで紹介したコンゴ・ミュージックのすべてとはいわないまでも大多数が、フランスのレーベル、ソノディスク(倒産後は親会社となったネクスト・ミュージック)を通じて世界へ配給されていた。しかし、そのネクスト・ミュージックまでも倒産してしまった。これまで、なんのために苦労してフランコやO.K.ジャズのレコードをレビューしてきたのか考えるとやりきれない気持ちになる。 |
||||||||||||||||
|
(7.10.05) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
前の画面に戻る |
||||||||||||||||